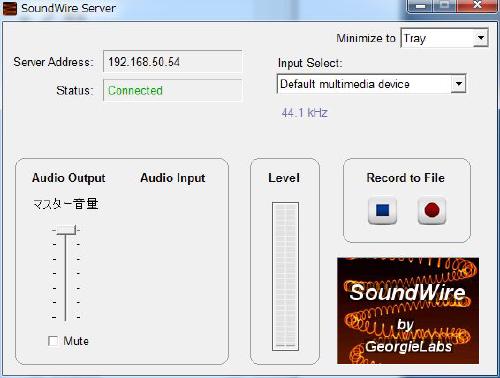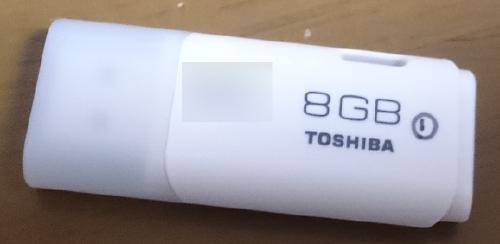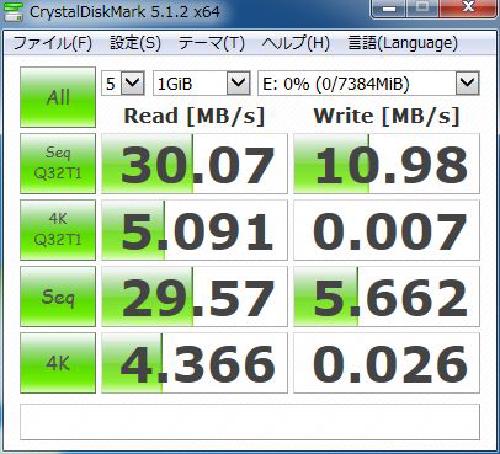去る12/1日、岡山県の笠岡ふれあい空港にてテストフライトを行ったのは既知の事実。
私は見てませんがあいテレビで特集まで組んでいただきましたので、愛媛県でご存知の方は結構多いのではないでしょうか。
一応今後の課題とか書いておかないとめんどくさそうなので、書いておきます。
電装:
・回転数計の表示がわかりにくい。あるライン超えたら音で知らせて欲しい
→回転数に応じてテンポが変わるブザー的なものが作れれば面白いかもしれない。PWMに応じて間隔が変化…とかないかな。
・電装基板が亀の子で増えていく…
→今回H/W割り込みを多用しているため基板がまとめられない。今後も無理。Arduinoの小型版とか導入してサイズを縮小したりとかはできそう。
・機速計のキャリブレーションせずに行った
→この件に関しては、出発当日、搭載を知らされたので俺は知りまっせーん
記録:
・ムービーと静止画、どちらを優先する?
今回、この問題は大きなフラストレーションになった。もちろん静止画のほうが綺麗に映るため、個人的には静止画がいい。
しかし、今回のTFでは、TV局が思ったような絵が取れず、結局こちらの映像をお渡しするという一幕があった。
更に…TF終了後に各方面から静止画はないかと突かれ、ないと答えると非常にdisられるという
……今回のTFは本当に嫌な思いをしました。はい。
・部員に関して
動画のほうがウケが良い。私がチェックする前にSDカードを渡せ渡せと急かす部員…てかOB?がいたくらいで、
これはこれで私のストレスの一つなのだがこの話は後で。要するに、静止画と動画どちらの需要もあるけれど結局どちらを優先するか微妙だった。部員各々勝手なことしか言わない。そして撮影者本人動画は半分嫌々撮っていて、「俺何のためにTF来たんだ?」と思いつつ参加していた。ということ。
現在、私が使えるカメラは計三台あり
・GF1
・EOS20D
・EOS7D
の三台である。今回20Dは持って行かなかったためGF1と7Dの二台体制。
//////今回のTFで判明したこと////
冬場の午前4~5時台の動画撮影は7Dに頼るしかないが、6時台、TFでメインとなる時間帯だとGF1でもなんとかなる
////考察////
基本的に、GF1=動画要員、7D=静止画要員として確保すればOK
20DはCFスロットが不調なので予備要員。
////悩みどころ////
今回、車載動画が非常に評判が良かった
→車載連写も取りたい…。
→車載用に20D(固定カメラ)を構え、自分は7D振り回して気持よく連写を取るのがいいのか?
7DでさえRAW連写は大変なのでJPGになるのかなーとも。
というか、滑走路の移動が非常に大変なので車1台必要だなとも…。
///次回プラン検討///
///プラン1///
一人でやるならこんな感じ。
・20Dを連写要因として車載
・7Dを動画要因として車載
→運転しつつ連写(リモコンなどで)
適当なタイミングで7Dを静止画要因へ切り替えて適当に撮影
///プラン2///
OBにお願いできるなら
車1
・GF1を動画要因(固定カメラ)
・20Dを静止画要員(固定カメラ)
車2
・7Dを静止画要因(自分撮影用)
移動が大変なので適当に車で先回りしつつ7Dを振り回せばいいのかなと
///総括///
記録って結構難しい…
私としては、TFであまり役に立てない分、しっかり記録に残すということを真面目に考えているわけで。
でも機材と人が足りないなーたまに翼端保持とかするしなー。
///愚痴///
今年度のTFを通して一番腹がたったのは
「動画まだー写真まだーサーバーアップまだー」の三連発である。
山越TFが終了して、大学に戻って、たった30分で
・ミーティングこなしつつ
・大量のRAW現像やら
・USB2.0のリーダーにCF読ませて100base-TのLANで鯖にコピー
など、できるはずがない。そしてコチラとしても一刻もはやく帰りたいわけである。というか他の部員はすぐ帰るわけである
それを、数名の部員の要望で、しばらく残ってデータコピー現像、鯖につながらないとクレーム対処…ストレスも溜まるわけである。
今回鳥人間をやめてやろうかとまで思った大きな原因はここらへんにあるので、次回からはしっかり意見したいと思う。
更に、今回二日間のTFで、私は途中実家に帰ったのだが(倒れそうだったので)、その車に乗る寸前にもも
「SDクレクレー」としつこく言われ、両親の前強く断れず渡したわけである…。
わがままいうようだが、自分で管理しているメディアを他人に渡すのは非常に抵抗がある。
バックアップ無しに渡したくないし、自分すらチェックしていないものを先に見られるのもあまり良い気がしない。
なお、自分でも驚いたが、
・自分は「データくれくれ人間」に対して驚くほど沸点が低い